近年、介護離職が社会的な問題として注目されています。
働きながら家族の介護をする人が増え、その数は約10.6万人(令和4年調査)※に達しているとも言われています。
特に、働き盛りの世代が介護と仕事を両立させるのに苦労しており、企業にとっても重要な課題となっています。
私のところにも、以前、介護離職に関する相談がありました。
相談者の方は、両親が共に介護が必要な状態になり、その責任を一人で負わなければならなくなったため、仕事を続けるのが難しく、辞職を考えていたとのことです。
しかし、私はその方に対して、仕事を辞めると老後の資金などに不安を抱えることになることを伝え、「辞めないように」とアドバイスしました。
また、別のケースでは、認知症を患っている親から何度も仕事場に電話がかかってきたり、近所の人から連絡があったりするなど、仕事中にも介護の問題が頻繁に起こっていました。
幸い、施設に入所できたおかげで、仕事を辞めることなく介護を続けることができました。
このように、在宅での介護は大変ですが、仕事を辞めることが後々の生活に大きな影響を与えることもあります。介護と仕事の両立を支えるためのサポートを活用し、慎重に考えることが重要です。
介護離職の原因

近年、介護離職が増加しています。少子高齢化や核家族化が進む中で、働き盛りの世代が介護と仕事の両立に苦しんでいます。
特に、自宅で介護を行うケースが増えており、その負担を一人で抱えることが多くなっています。
〈介護離職の主な原因と考えられるもの〉
- 支援制度の未活用
公的な介護保険や福祉サービスがあるものの、利用方法がわからず十分に活用されていないケースが多く見ら
れます。
- 施設から在宅介護へ
国の政策として、施設介護から在宅介護への流れが進んでいます。これにより、特別養護老人ホームなどへの入所が難しくなり、自宅での介護が必要となる場合が増えました。
例えば、特別養護老人ホームへの入所基準が、以前は「要介護1」以上だったのが、現在では「要介護3」以上に引き上げられています。このため、家族が介護を担う負担が増大しています。
- 医療技術の進歩
医療技術の向上により、高齢者の寿命が延びています。しかし、その反面、長生きすることで介護が必要とな
る時間も長引くことになります。このような状況が続くことで、介護の負担が一層重くなり、離職を余儀なく
される人々が増えています。
介護離職が引き起こす経済的な問題
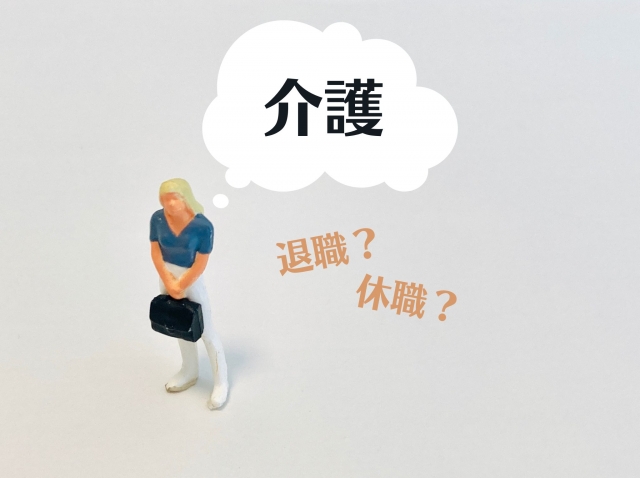
介護離職は、個人にとっての問題にとどまらず、経済全体にも大きな影響を及ぼします。
仕事を辞めることで収入が途絶え、預貯金を取り崩さざるを得なくなります。
また、場合によっては自宅などの資産を売却しなければならないこともあります。
その結果、生活費が足りなくなり、経済的に困窮するケースも少なくありません。
さらに、介護が終了した後も、自分の老後資金を確保するのが難しくなることが予想されます。
また、長期間の介護生活が続くことで、キャリアにも大きな影響を与えることになります。
親の介護が終わったときには、年齢的のも再就職が難しくなり、職業人生が大きく変わってしまうことも多いです。
企業にとっての介護離職の影響
企業にとって、介護離職が増えることは重要な課題です。
人材を失うことで業務の効率が低下し、経営に悪影響を及ぼすことがあります。
特に中小企業では、限られた人員で業務を回している場合が多く、離職による影響が大きいです。
企業としても、従業員が介護と仕事を両立できるよう、柔軟な働き方の導入や支援策を講じることが求められます。
介護離職を防ぐための解決策

まとめ
介護離職は、本人だけでなく家族や職場、社会全体に影響を与える問題です。
しかし、適切な制度を活用し、企業と従業員が協力して取り組むことで、介護と仕事の両立は可能になります。
柔軟な働き方や制度の活用を通じて、働きやすい環境を整えることが重要です。
また、介護や生活に関するさまざまなテーマについて、介護ポストセブンでも取り上げています。こちらの記事もぜひご覧ください。
メディア掲載実績
私のコメントや情報提供を行った記事が、以下のメディアに掲載されています。詳しくはこちらをご覧ください。