親が高齢になってくると、少しずつ「もしも」の備えを考える方が増えてきます。
その中でも多いのが、介護にかかるお金の不安です。
「介護にはどれくらいかかるのか」「今ある親のお金で足りるのか」「自分たちの生活にも影響が出るのではないか」と、漠然とした不安を抱えながら、日々の暮らしを送っている方も多いのではないでしょうか。
実際に介護が始まると、最初は在宅で何とかやりくりしていても、次第にデイサービスや訪問介護、施設入所など、選択肢が広がると同時に出費も増えていきます。
問題なのは、そのタイミングで親が認知症になり、判断力が低下していると、「親の口座から必要なお金を引き出すことすら難しくなる」ことがある、という点です。
「うちの親の年金でやりくりすればいい」と思っていても、その口座が凍結されてしまったら、介護費用が払えず、結果として家族が立て替えることになるケースもあります。
現に、私の身近にも、親の介護サービスなどの支払いを、子どもが一時的に立て替えたという事例がありました。
介護にはお金も手間もかかりますが、さらにその費用をどうやって出すかという“資金の動かし方”まで考えておかないと、現場で立ち往生してしまう可能性があるのです。
こうした状況を防ぐために、元気なうちから準備しておきたいのが「任意後見制度」です。
任意後見とは何か?将来に備える「契約」の仕組み

任意後見制度とは、本人がまだ元気で判断能力があるうちに、「将来、自分の判断力が衰えたときのために、財産管理などを代わりに行ってくれる人(後見人)を自分の意思で選んでおく」仕組みです。
この制度を利用するには、公証役場で「任意後見契約」を公正証書で結ぶ必要があります。
契約が結ばれると、公証人によってその内容が法務局に登記されます。
この登記によって、将来、任意後見人が財産の管理や各種手続きを行う際に、必要に応じて「登記事項証明書」を取得し、法的に代理権を証明できるようになります。
ただし、契約を結んだ時点ですぐに任意後見がスタートするわけではありません。
本人の判断能力が実際に低下してきたタイミングで、親族や任意後見受任者などが家庭裁判所に「任意後見監督人の選任」を申し立てます。
家庭裁判所が監督人を選任した段階で、正式に任意後見契約が発効され、任意後見人としての権限が有効になります。
それまでは「任意後見受任者」としての立場にとどまります。
この制度の最大の特徴は、「誰に後見を任せるか」「どのような支援をしてもらうか」を、あらかじめ本人の意思で決めておけるという点です。
たとえば、「医療や介護サービスの契約」「介護施設への入所手続き」といった身上に関することや、「銀行口座の管理」「不動産の管理」といった財産に関する内容など、具体的な事務の範囲を契約書の中で明確に定めることができます。
内容はある程度自由に設計できますが、注意点もあります。
たとえば、次のような内容は代理権に含めることができません。
-
本人の身分行為(結婚・離婚など)や契約の取消し
-
掃除や洗濯などの実際の介護や家事といった“事実行為”
-
本人が亡くなった後の諸手続き(死後事務)
-
延命治療の中止など、命に関わる医療行為の代理
また重要なのは、認知症などで判断能力が不十分になってしまった後では、任意後見契約を新たに結ぶことができないということです。
つまり、「いざというとき」では間に合わないのです。
だからこそ、まだ元気なうちに、自分のお金や暮らしをどう守っていくか、誰に任せるかをしっかり考え、「お金の流れが止まらない仕組み」を準備しておくことが、将来の安心につながります。
任意後見制度は、介護生活に直面したときに「備えていてよかった」と思える、心強い制度のひとつなのです。
※参考 日本公証人連合会 任意後見契約
成年後見制度との違いに注意

任意後見制度と混同されやすい制度として、「法定後見制度」があります。
いずれも成年後見制度の枠組みに含まれる制度ですが、その性質や制度の始まり方には大きな違いがあります。
法定後見制度は、すでに認知症などで判断能力が不十分になってしまった人のために、家庭裁判所が後見人を選任する仕組みです。
このとき、たとえ家族が「自分が後見人になりたい」と申し出ても、必ずしもその希望が通るわけではありません。
実際には、司法書士や弁護士、社会福祉士といった専門職が後見人に選ばれることが多くなっています。
令和6年1月から12月の「成年後見関係事件の概況」(最高裁判所事務総局家庭局)によると、選任された後見人のうち親族は17.1%、親族以外が82.9%を占めています。
その内訳としては、司法書士が34.7%、弁護士が25.7%、社会福祉士が20.1%と、専門職が大多数を占めているのが現状です。
また、申立書に親族を候補者として記載しているケースは約21.3%にとどまっており、実際に親族が後見人に選任される割合はさらに低いことがわかります。
さらに、この制度が開始されると、親の財産を動かす際には裁判所への報告義務や許可が必要となり、たとえ家族であっても自由に通帳からお金を引き出したり、不動産を処分したりすることができなくなります。
つまり、本人の財産は厳格に管理されることになり、その分、家族の自由度が大きく制限されるという現実があります。
一方で、任意後見制度は、本人がまだ元気で判断能力があるうちに、自分の意思で「将来、判断力が低下したときに財産管理などを任せたい相手」を決めておくことができる仕組みです。
契約は公正証書で行われ、本人の意思によって内容を柔軟に決めることができます。
そして実際に判断能力が低下したときに、家庭裁判所に申し立てて任意後見監督人が選任されて初めて、後見がスタートします。
このように、法定後見制度と任意後見制度の大きな違いは、「始まり方」にあります。
法定後見はすでに判断能力がなくなった人のための制度であり、任意後見は将来の備えとして、本人が自分の判断で選び取ることができる制度です。
介護費用などお金の管理が必要になる場面を考えたとき、いざというときに慌てて法定後見に頼らざるを得ない状況を避けるためにも、判断能力のあるうちに任意後見契約を結んでおくことが、家族にとっても本人にとっても大きな安心につながるのではないでしょうか。
任意後見契約にかかる費用と手続き
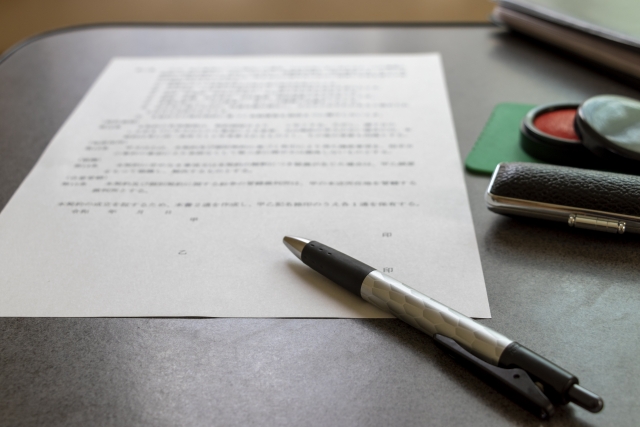
任意後見契約は、公証役場で「公正証書」による契約を結ぶことが法律で定められています。
契約にかかる費用としては、公証人の手数料を含めておおよそ2万円程度が必要です。
具体的には、公正証書作成の手数料が約11,000円、法務局に納める登記のための収入印紙代が2,600円、登記嘱託手数料が1,400円、そしてそのほかに若干の雑費がかかります。
※参考 成年後見制度 法務省民事局
この契約書を作成する際、行政書士や司法書士などの専門家に相談・依頼する場合は、別途5万円から15万円程度の報酬がかかるのが一般的です。
任意後見契約は、契約を結んだ時点では効力は発生しません。
実際に本人の判断能力が低下し、契約が発効するときには、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる必要があります。
この際にも手続き費用がかかり、申立手数料(収入印紙800円)、登記手数料(収入印紙1,400円)、さらに郵便切手代などが必要になります。
※参考 任意後見制度とは 厚生労働省
任意後見が開始されると、家庭裁判所が選任する任意後見監督人に対して、管理財産額が5000万円以下の場合、月額1万円〜2万円程度の報酬が支払われるのが目安になります。
なお、任意後見人が家族や親族である場合、その報酬は本人や契約内容次第で任意に設定できますが、専門職が任意後見人になる場合は必ず報酬が発生します。
報酬額は専門家によって異なるため、詳細は各専門家に直接問い合わせることが望ましいでしょう。
このように、任意後見制度の利用には一定の費用がかかります。
金額だけを見ると「少し高い」と感じるかもしれませんが、判断能力が低下してからではできることが大きく限られてしまう現実を考えると、将来への備えとして“保険”のような価値を持つ制度だといえます。
また、任意後見制度には3つの利用形態があり、それぞれの状況や目的に応じた選択が可能です。
ひとつ目の「即効型」は、契約締結後、すぐに任意後見契約の効力を発生させるタイプで、すでに判断能力が低下し始めている場合などに利用されます。
ふたつ目の「将来型」は、契約は結ぶものの、本人の判断能力が低下するまでは実際に代理権を発生させず、必要になるまではそのまま保留される形態です。
そして「移行型」は、契約締結と同時に委任契約に基づく任意代理権を先に発動し、将来的に本人の判断能力が衰えた段階で任意後見契約へと移行する方式です。
それぞれの利用形態にはメリット・デメリットがありますが、自分自身や家族の将来を見据えて、どのタイミングでどのように備えるかを考えておくことが、後悔のない判断につながるはずです。
まとめ

介護費用の備えというと、「どれくらい貯金しておけば安心か」「保険に入るべきか」といった「お金」の問題に意識が向きがちです。
でも実際には、「誰が、いつ、どうやって、そのお金を使うか」という「仕組み」を整えておくことが、安心な介護生活を送るためには欠かせません。
任意後見制度は、まさにその仕組みづくりの一つです。
親のお金を守るだけでなく、必要なときに必要な介護を受けられるようにするための大切な手段でもあります。
「今はまだ早いかな」と思う段階こそ、じつは検討するベストなタイミングです。
将来のために、ご家族と一緒に話し合ってみてはいかがでしょうか。
もし「何から始めればいいのか分からない」「うちのケースで本当に必要なの?」と迷っているなら、ぜひ一度ご相談ください。
あなたの状況に合わせた準備の仕方を、一緒に考えていきましょう。
また、介護や生活に関するさまざまなテーマについて、介護ポストセブンでも取り上げています。こちらの記事もぜひご覧ください。
メディア掲載実績
私のコメントや情報提供を行った記事が、以下のメディアに掲載されています。詳しくはこちらをご覧ください。
【最近のご相談例】
・介護費用がどれくらいかかるのか不安(50代女性)
・親の遺言書・生前贈与について(40代男性)
・資産運用について基本を整理したい(60代女性)など
【過去の一部の相談事例】
・介護費用に関連する補足給付について(50代女性)
・医療費控除の概要について(50代女性)
・親の有料老人ホームの費用に関するキャッシュフロー表作成(50代夫婦)
・親の収入や資産から子どもへの援助に関するキャッシュフロー表作成(50代女性)
・親の保険と介護費用に関するご相談(50代女性)
・自宅の民事信託の活用と概要について(50代男性)
・所得控除と介護費用の関連について(60代女性)
・金融機関の解約手続きについてのご相談(60代女性)
・遺産分割協議書の作成に関するご相談(60代女性)
・親の介護費用と一時払終身保険の活用について(50代女性)
・老後資金のキャッシュフロー表作成(60代男性)
・年金受給に関するご相談(60代男性)など
※初回20分無料相談受付中です。お気軽にご連絡ください。
親の介護、準備できていますか?チェックリスト10

「親が後期高齢者になったけど、何を準備すればいいかわからない…」
そんな方のために、今すぐできるチェックリストをご用意しました!
✅ 親の年金額と貯蓄額を把握している(はい・いいえ)
✅ 親が要介護になった場合、どのくらいの費用がかかるか試算したことがある(はい・いいえ)
✅ 介護費用をどこから出すのか決めている(親の資産・子どもの援助など)(はい・いいえ)
✅ 親の銀行口座や財産を管理する方法(家族信託・成年後見など)を考えている(はい・いいえ)
✅ 親が認知症になったときの財産管理・手続きをどうするか決まっている(はい・いいえ)
✅ 介護施設に入る場合の費用や条件を調べたことがある(はい・いいえ)
✅ 介護費用の公的支援制度(高額介護サービス費・税控除など)を理解している(はい・いいえ)
✅ 兄弟姉妹と介護費用や負担について話し合ったことがある(はい・いいえ)
✅ 介護が必要になったとき、誰が主に対応するのか家族で合意している(はい・いいえ)
✅ 親と「介護が必要になったときの希望」について話したことがある(はい・いいえ)
✅ 「はい」が0~5つの方へ
介護費用や生前対策が不十分な可能性があります。
いざというときに困らないために、今のうちに対策を進めましょう!
